ニュース・お知らせ
新たに注目される「市民後見人」
浅川澄一 [福祉ジャーナリスト(前・日本経済新聞社編集委員)]
相次ぐ家族後見人による「横領」
成年後見は、家族制度より法的には上位に位置する。3年ほど前に、85歳の父親から9000万円の預金を横領したとして53歳の娘とその夫が山梨県甲府市で逮捕された。2009年2月に金融機関で父親名義の口座から現金を引き出した疑いだ。「事業資金に使った」と両容疑者は供述しているという。
家族の金を持ち出しただけなら、多くの家庭でよくあること。犯罪ではない。なぜ、逮捕されたのか。実は、娘は父親の成年後見人として甲府家裁から選任されていたからである。後見人になると家族でも「他人の関係」となる。
いったん後見人に選任されると、家族だからといって勝手に被後見人の財産を使い込むことは許されない。
刑法では特例として「直系血族や同居する親族間の窃盗や横領は刑を免除する」とあるが、最高裁は「成年後見には公的な性格があり、財産を誠実に管理すべき義務がある」という判断を示している。特例は適用されない。だが、同様の横領事件は全国で相次いでいる。
最高裁の調査では、親族後見人らが勝手にお金を引き出した総額は、2011年は約33億4000万円、12年は約48億1000万円、13年が約44億9000万円にのぼる。このため裁判所によって後見人を解任された事例も多い。
法定後見の利用者は年々増え続け、2013年中に選任された後見人は3万4215件で、2001年の2.6倍に増えている。2013年度末時点では17万6548人に達している。
その不祥事が増えたのは、「家族内の財産は皆で使っていい。親の財産はどうせ相続するもの、という気持ちがあるから」と関係者は指摘する。
後見制度は個人が対象。東アジアに共通する伝統的な一心同体の家族観がまだ根強い中で、個人単位に舵を切ったのが介護保険制度であり、成年後見制度である。日本の社会保障や税制度のほとんどは個人でなく、家族を単位として成り立ってきた。年金の第三号被保険者や配偶者控除はその代表例だろう。子供に親の扶養も義務付けた民法を持つ国は欧米にはない。
「親族後見は利益相反になりがち。本人よりも相続人としての損得勘定で動いてしまう」と弁護士の堀田力氏は強調し、「後見人として適格性を欠く例が少なくない」とも断じる。
制度発足時には親族後見人が圧倒的に多数を占めていた。その後、司法書士をはじめ社会福祉士や弁護士、行政書士などの法律や福祉の専門職が乗り出す。そのため2000年には94%だった親族後見が2013年には43.2%と減少してきた。代わって、司法書士をはじめ専門職の後見人が急増し57.8%に膨らんでいる。
だが、専門職後見人には人数の限界がある。一方で認知症高齢者は既に460万人に達しており、これから団塊世代が介護保険利用者となるとともに、後見の必要者は急増していく。
また、都会部を中心に身寄りのない一人暮らし高齢者や老々介護状態の夫婦世帯も確実に増えていく。現状でも後見人のなり手は足りない。契約の当事者にはなれない本人に代わって、家族が利用契約書にサインするということも頻出しており、「私文書偽造に問われかねない」と指摘する法律の専門家もいる。新たな後見人が必要とされているのは明らかである。

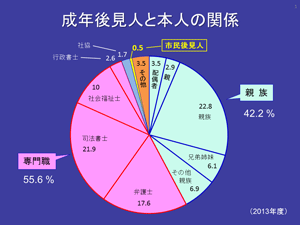



![[画像]市民後見センターおおさかキャラクター](/images/common/character.gif)